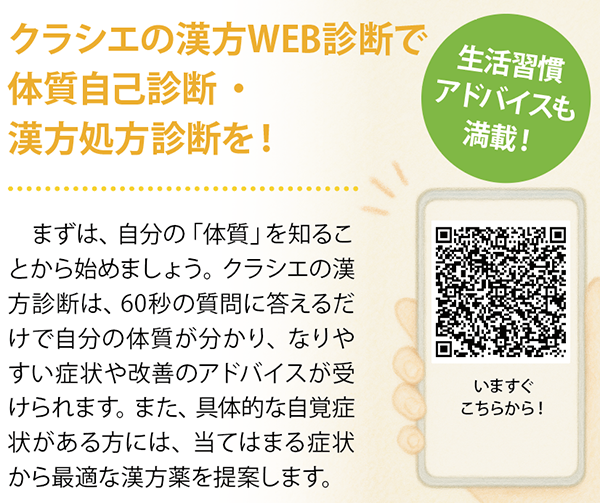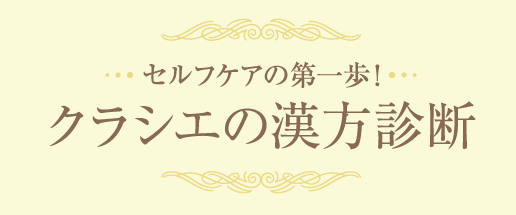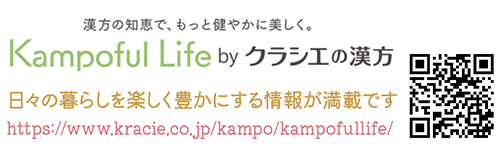漢方薬の研究開発や製造販売で歴史と実績のあるクラシエが運営する情報サイト「Kampoful Life(カンポフルライフ)」とのコラボレーションによって、毎日をすこやかに暮らすための漢方の知恵を紹介しています。今月は、サイト内の「カラダ」のコンテンツから、多くの人にかかわりのある「冷え」を取り上げます。
*カネボウ労連クラシエ労働組合はUAゼンセンの仲間です。
「冷え」と聞くと、秋から冬にかけての不調というイメージがありませんか。実は、冷えは年中起こる可能性がある不調の代表格です。自覚症状の有無や、全身が冷えるタイプ・カラダの一部が冷えるタイプなど、人によっても異なります。今回は、そんなだれにでも起こり得る「冷え性」を漢方の視点から解説します。

「末端冷え性」から「のぼせ冷え」まで
原因と対策、冷え性改善のポイント
近ごろ、年齢や性別を問わず問題となっているのが「低体温化」です。平熱が下がってくるとカラダがより冷えやすくなり、体調にも少なからず影響をもたらします。慢性的な冷えが続くと、免疫力が下がって風邪をひきやすくなったり、肌あれやむくみを引き起こしたり、月経トラブルや便秘に悩まされたりします。
漢方では冷え性が、「気」や「血(けつ)」の巡りを滞らせ、カラダ全体のバランスを崩すことにより、“万病のもと”になると考えます。
冷える部位や体質によって、ケアの方法は変わってきます。そのため、まずは自身の「冷えタイプ」を見つけましょう。
【ほてりも下半身の冷えもある「のぼせ冷え」】
上半身は汗をかきやすかったり、ほてったりするのに、下半身は冷えている。そんなタイプは、更年期や自律神経の乱れが原因の1つとして考えられます。溜まったストレスの解消を心がけ、リラックスできる時間をつくりましょう。
【手足のみが冷える「末端冷え性」】
カラダの栄養のもととなる「血」が不足していたり、巡りが悪くなっていたりするタイプです。気温が下がってくると、手足が冷たくなる傾向があります。日ごろからカラダを温める習慣を意識したり、軽めの運動を取り入れたりしましょう。
【全身が冷える「エネルギー不足」】
カラダを温める「気」が不足している可能性があります。胃腸が弱っているケースも考えられます。タンパク質やミネラル豊富な食事を取り、栄養補給を心がけましょう。過度なダイエットは「気」を消耗するので控えることをおすすめします。
漢方薬で冷え性を改善
漢方薬のなかにも、冷え性の改善に効果が期待できるものがあります。冷えを感じる部位や、自身の体質に合わせて漢方薬を選び、悩める冷え性の改善に役立ててください。
【のぼせと下半身の冷えが両方ある方へ―加味逍遙散(かみしょうようさん)】
女性と関係の深い当帰(トウキ)や芍薬(シャクヤク)、白朮(ビャクジュツ)、茯苓(ブクリョウ)、柴胡(サイコ)、牡丹皮(ボタンピ)、山梔子(サンシシ)、甘草(カンゾウ)、日本人に馴染みのある薄荷(ハッカ)や生姜(ショウキョウ)といった10種類の生薬(しょうやく)を配合し、更年期や月経トラブルなど婦人科系の不調をケアする漢方薬としても知られています。疲れやすいタイプの冷え性などに使われます。
【手足が冷える末端冷え性に悩む方へ―当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)】
カラダを温めることで熱を作り出す働きを手助けする漢方薬です。冷えによる頭痛や腰痛といった痛みなども改善する効果が期待できます。古くから香辛料としても重宝されてきた桂皮(ケイヒ)や当帰、芍薬、木通(モクツウ)、細辛(サイシン)、甘草、呉茱萸(ゴシュユ)、生姜、別名「ナツメ」とも呼ばれる大棗(タイソウ)など9種類の生薬を配合し、手足の末端冷え性に効果をもたらします。
【手足が冷えるエネルギー不足な方へ―人参養栄湯(にんじんようえいとう)】
体力が低下し、疲れや食欲不振を感じている方におすすめの漢方薬です。消化器の働きを高め、「気」や「血」といった必要な栄養をカラダのすみずみまで行き渡らせることによって、冷えを改善します。生薬の代表格でもある人参(ニンジン)や当帰、地黄(ジオウ)、白朮、茯苓、芍薬、陳皮(チンピ)、遠志(オンジ)、黄耆(オウギ)、桂皮、五味子(ゴミシ)、甘草といった12種類の生薬を配合。エネルギー不足による手足の冷えに働きかけます。
「頭寒足熱」を心がけて
漢方の視点から考える理想のカラダは、下半身が温まっていて、頭がすっきりと冷えている「頭寒足熱(ずかんそくねつ)」の状態だといわれています。逆に心配なのは、頭は熱を帯びているのに、下半身は冷えている状態です。
下半身をよく温め、カラダの上部に血液をスムーズに送り出せるライフスタイル(食事、運動、入浴)を心がけましょう。