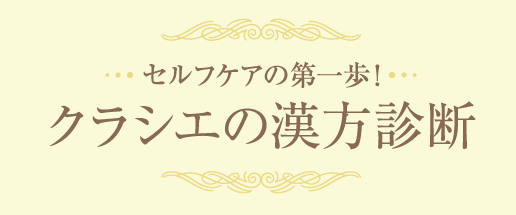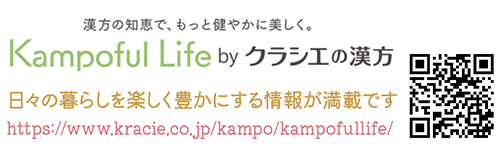漢方薬の研究開発や製造販売で歴史と実績のあるクラシエが運営する情報サイト「Kampoful Life(カンポフルライフ)」とのコラボレーションによって、毎日をすこやかに暮らすための漢方の知恵を紹介します。今月は「カラダ」のコンテンツからいまの季節に注意したい「秋バテ」を取り上げます。
*カネボウ労連クラシエ労働組合はUAゼンセンの仲間です。
過酷な夏も過ぎ去り、過ごしやすいはずの秋に入ったのにカラダがだるい、疲れが取れない、ヤル気が出ない…、そんな症状に心当たりのある方は、もしかしたら「秋バテ」かもしれません。今回は意外と多い「秋バテ」の原因と対策について紹介します。

秋は体調を崩しやすい季節 意外と多い「秋バテ」に注意
「夏バテ」に比べると、あまり耳なじみがありませんが、秋バテで悩む人は意外と多く、最近少しずつ認知されるようになってきました。主な症状は、夏バテに似た次のようなものです。
- カラダがだるい
- 疲れが取れない
- ヤル気が出ない
- 頭が痛い
- めまいがする
- 食欲がない
- 胃がもたれる など
なぜ、秋バテは起こるのでしょうか。カラダは自然環境とバランスを取りながら健康を保っています。気候が変化すれば、その変化に合わせてカラダも順応させなければなりません。暑く湿気の多い夏から、涼しく乾燥した秋へ変わる気候の変化にカラダもついていくのがやっとです。
秋は「女心と秋の空」と言われるように、天気の変化と1日の寒暖差がとても大きい季節です。日中はまだ夏を引きずったかのように暑いのに、朝晩は驚くほど冷え込むので、カラダも体温調節に必死です。そんな変化の多い秋に、夏の疲れを引きずったまま突入してしまうと、カラダは悲鳴をあげて、秋バテの症状がみられるようになるのです。
秋に体調不良になる要因
秋は気温が急に変化するため、自律神経が乱れやすく、カラダの負担が大きくなります。夏の疲れがカラダに蓄積されていることもあり、胃腸が弱っている人はとくに不調を感じやすくなります。
また、日照時間が短くなると、幸福感を得るために欠かせない脳の伝達物質である「セロトニン」の分泌が減少するため、気分が不安定になり、イライラや不眠が増えることもあります。
乾燥した空気も体内の水分を奪い、血行不良や疲労感を引き起こします。免疫力が低下することも体調不良につながりやすい要因です。
秋バテにならないためには、まずは変化に対応できるだけの体力をつけることが大切です。夏の疲れをしっかりリセットして、元気ですこやかなカラダを取り戻しましょう。
「食養生」で秋バテを改善
漢方では、湿気の多い梅雨から夏に胃腸は弱りやすく、逆に、乾燥しやすい秋から冬には食欲も上がり調子も出てくると言われています。秋は「食欲の秋」と言われるように、本来であれば胃腸のコンディションが良くなる季節。秋バテで食欲がないなど胃腸の弱りを感じている人は要注意です。
カラダを動かす原動力は食べたものからつくられます。胃腸が弱っていると元気も出ませんよね。胃腸に不安を感じている人は、まずは胃腸を整えることから始めることが先決です。
秋バテには、だれにでも簡単に始められる食養生がおすすめです。ポイントは、“旬をいただく”こと。
旬の食材はおいしく栄養が豊富なだけでなく、その季節のトラブルに対応したうれしい働きがたくさん詰まっています。ぜひ、槇玲(まり)先生の薬膳レシピのコラムも参考にしながら、食養生を始めてください。
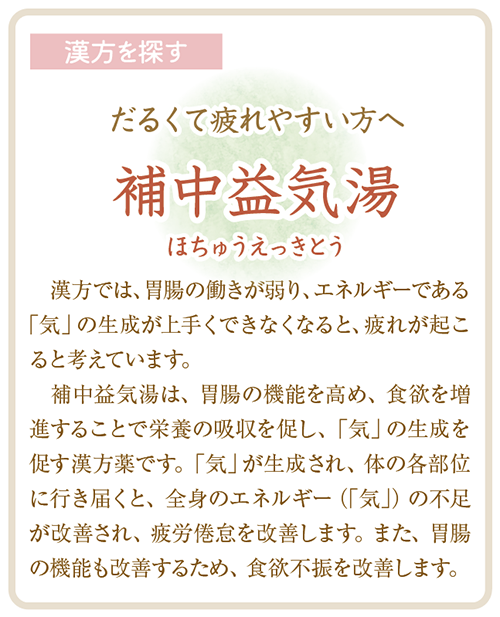

クラシエの漢方WEB診断で 体質自己診断・漢方処方診断を!
まずは、自分の「体質」を知ることから始めましょう。クラシエの漢方診断は、60秒の質問に答えるだけで自分の体質が分かり、なりやすい症状や改善のアドバイスが受けられます。また、具体的な自覚症状がある方には、当てはまる症状から最適な漢方薬を提案します。